こんにちは!くじらパパです。
今回もADHDの話です。ADHDに限らず発達障害の困りごとはある程度パターンがあり、年代によって大きく異なっていること知られています。
今回は特に小学生の頃によくみられる、4つの問題について分かりやすく説明してみましたのでぜひ参考にしてみてください。
今回の記事は以下の人にお勧め!

- 小学生のADHDで起きやすことは?
- なぜ上手く行かないのか知りたい。
- 対応の仕方は?
なぜ年代で異なるのか?

ADHDの問題は、能力と環境とのミスマッチにより起こります。
環境とは例えば、
小学校:学校や家族との関係
思春期:塾や部活、友達や異性との関係
大人:会社や地域、パートナーや子供との関係
など年代によって様々な環境があります。
ADHDの特性はその時々で影響を与えますが、起こりやすいことは年齢ごとにパターンが違います。
今回は小学校の頃に起こりやすい、学校や家庭での問題について解説してみようと思います。
落ち着かない

ADHDと聞いて一番イメージしやすいのは落ち着きが無いことではないでしょうか?
「授業中に立ち歩く」、「当てられてないのに答えを言おうとする」などがあり、特に低学年の頃に目立ちやすいです。目立たなくなっても完全には無くならないこともあります。

また、ADHDの子供は事故やけがをしやすいと言われています。
道路から飛び出しそうになる、危ないものでも触ろうとするなどを起こしやすいです。注意力も弱いため、転んだり物にぶつかったりすることもあります。

理由は、ADHDの特性である多動性や衝動性です。
不注意型が優位の子どもは目立たないこともありますが、これらの特性がある場合、周囲の人は見守ってあげないといけません。
ADHDを知らない人からは、「子供は動き回るくらいが普通だよ」とか「しつけがなってないんじゃない?」などと誤解されやすいのもつらいところです。
診断が付くことで、このような誤解を防げることは一つのメリットになります。
大人や友達と協力する

落ち着きがないこと以外にも、ADHDの特性で困ることがあります。
それは、周りの人と協力して行動することが苦手な事です。
例えば、日常のやるべきこととして
- 明日の準備をする
- 時間通りに行動する
- ルールや約束を守るなど
などやるべき行動があります、ADHDの人はこれらが上手にできません。
そこで、親や先生など周りの人にサポートをもらないがら協力して達成する必要があります。
ですがADHDの特性から言われてもすぐにできなことが頻繁にあり、親からすると何度も声を掛けなどのサポートをしなければならなくなります。

時には、指示されたことに反抗的な態度をとってしまう子もいるため、家族の関係がイライラしだして怒りが爆発するきっかけなってしまいます。
これを防ぐためには、上手くできないのは怠けているからではなく、脳の実行機能の障害が原因であることを理解してあげる必要があります。
また、支援する人がサポート疲れにならない様、余裕をもてる環境をつくらなければなりません。
見通しをもたせる、視覚補助を取り入れる、行動療法的アプローチを行うなどの様々な工夫も有効になります。
コミュニケーションとる

コミュニケーションの問題というと、発達障害の中でも自閉症スペクトラム特有の物と思う人もいると思いますが、実はADHDでも問題となることがあります。
コミュニケーションとは、単に言葉をたくさん知っているかどうかの知識の問題ではなく、場面に応じて言葉を使い分ける力が必要です。
場面に応じるとは力とは例えば、相手の表情を読み取る、いらない情報は捨てる、伝わっているかどうかを確認するなどの能力が必要がです。
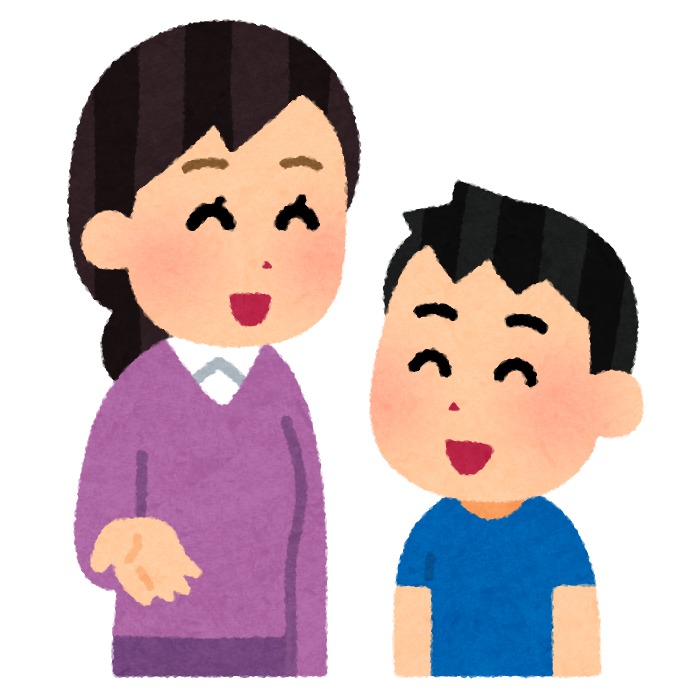
ADHDの人はこの機能が上手く働かず、自分の考え上手に伝えたり、相手が言いたいことを理解することが苦手になります。
さらに、思ってことがすぐに言葉でててしまい誤解やトラブルが起きやすくなってしまいます。
この様な理由で、ADHDの人はコミュニケーションが取りずらいことをよく起こるのです。
勉強をする
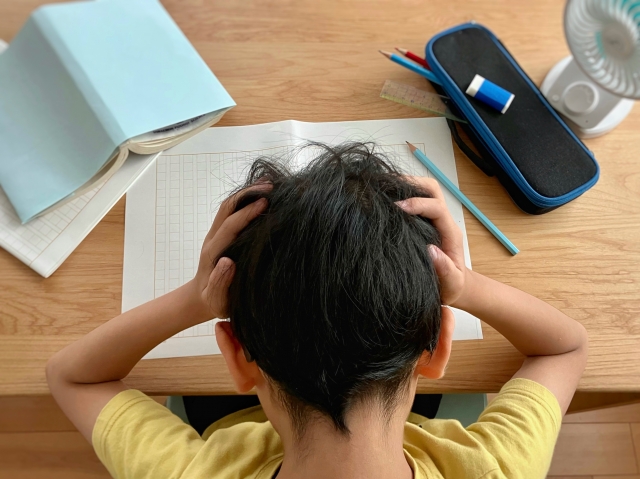
ADHDの子供は勉強がつまずきやすいです。
原因は様々ありますが、その一つに「ADHDの人は、集中して粘り強くこつこつすることが苦手」という特性があるからと考えられます。
授業や宿題の時間に、じっと座って問題を解き続けるという行動が苦痛でたまらないのです。
さらに、勉強中に他の事が気が散ったり集中力が続かないことも起こります。
そうなると、やはり知識の定着には時間がかかってしまいます。
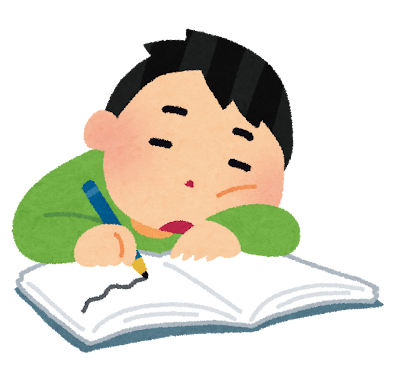
勉強に対するやる気も下がりやすくなります。
ADHDの子供は不注意の症状があるため、細かいミスで減点を喰らいやすくなります。
例えば、「漢字のとめ・はね」、「くり上がり・くり下がりの計算」など。
ミスにより他の子供より×を付けられる機会が増えてしまいます。
さらに、せっかく頑張って勉強が分かるようになっても、得られる達成感が他の人より少ないことも言われています。(報酬系の障害といいます)
結果として勉強のモチベーションがあがらず、苦手意識がついてしまいますます勉強から遠ざかってしまう悪循環になってしまいます。
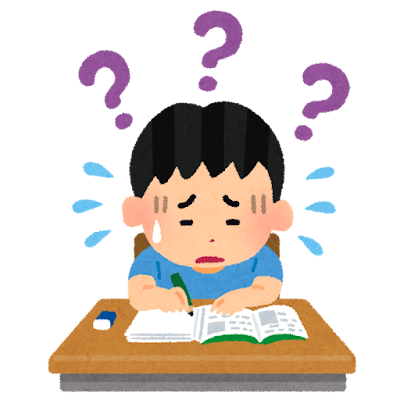
ADHDの子供は、LD(学習障害)という別の障害を併発しやすいことも研究で明らかになっています。
集中力やモチベーションの問題だけでなく、そもそもの勉強の苦手さがないかも評価していくことが大切です。
まとめ
今回は、小学生の頃に起こりやすいADHDの困りごとのパターンについて紹介してみました。
- 落ち着かない
- 大人や友達と協力する
- コミュニケーションをとる
- 勉強をする
この年代の子供達へは、自分で問題を対処する力を身に着けるまでは、周囲の大人が守り、導いてあげる必要があります。
さらに、自分の能力を超えそうな課題に直面した時には、サポートを与える一方で、子供がもっと自分でやってみたいことを認め、励ましてあげることが大切です。
挑戦する課題が、今の子供で乗り越えられる課題なのかどうかを見極め、どんな支援がいるのかなどを専門家などと話し合いながら進めていってください。


